【国公立理系】8月から二次試験までのスケジュール
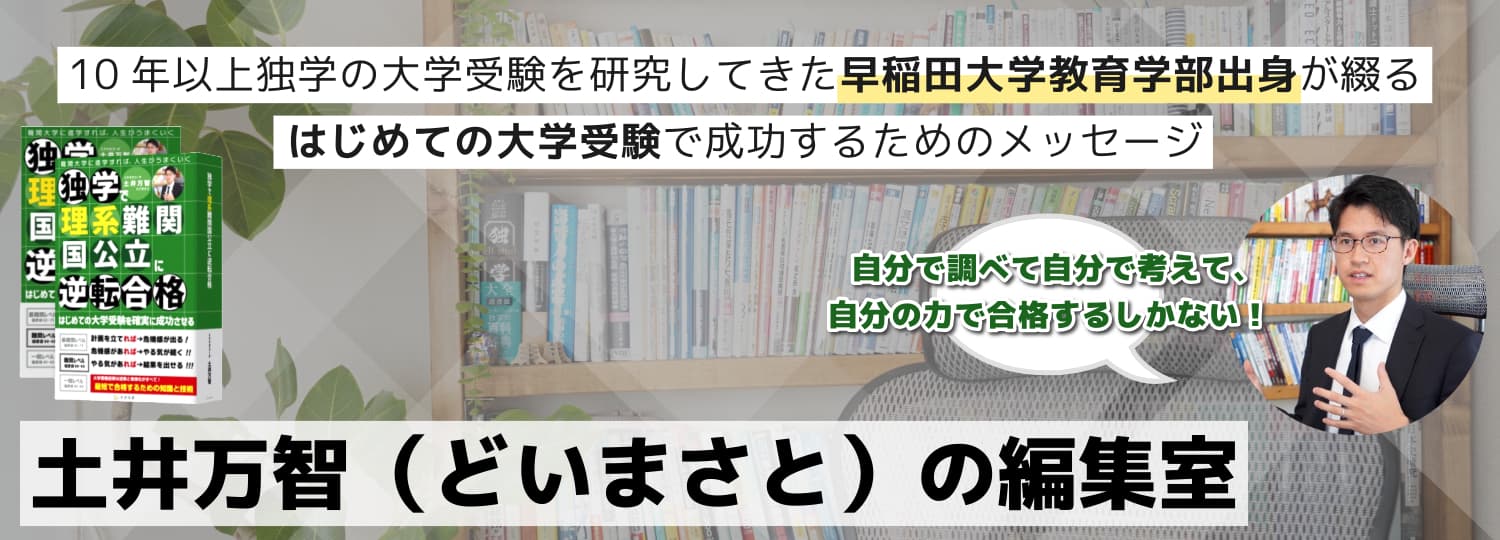
国公立理系の夏以降のスケジュールは超!複雑!です。
「決めなきゃいけないことも多いのに、決める判断基準も難しい!」
そんな国公立理系ですが、共通テストと二次試験と私立大学を予想しながらスケジュールを立てます。
ぜひ、ついてきてください!

土井万智(どいまさと) 独学で大学受験に効率よく成功する攻略法
早稲田大学教育学部出身。大手予備校スタッフの経験から大学受験にかかる費用や時間に疑問を持ち、在学中にウェブメディア「イクスタ」を立ち上げ。現在ウェブメディアとYouTubeチャンネルとオンライン予備校の 【イクスタコーチ】を運営。イクスタコーチ卒業生の進学先の平均偏差値 63.4(偏差値は東進ハイスクール参照)著書に『独学で難関大学【理系】に逆転合格する』。
コーチ、 参考書ルート、 参考書比較チャート、 カレンダー、 初心者ガイド、 YouTube、 インスタ
8月から二次試験の本番まで、
各科目の基礎、各科目の演習レベル、二次試験の過去問、共通テストの過去問、私立大学の過去問をそれぞれどのタイミングでどれくらいのバランスで進めていけばいいのか、決め方をご案内します。
4つの時期に分けてご紹介します。
①8月の夏休み
②9月から11月末
③12月第1週から共通テスト本番
④共通テストから二次試験
4つの期間のテーマ
二次試験から逆算するとやるべきことが決まります。
共通テストから二次試験まで
◯ 二次試験の過去問
◯ 私立大学の本番
◯ 私立大学の過去問
12月第1週から共通テスト本番
◯ 勉強時間の8〜9割は共通テスト対策
└ 知識のインプットと過去問と共通テスト実戦問題集
◯ 1〜2割は二次試験レベルの演習
9月から11月末まで
◯ 二次試験と私立で使う科目の入試レベルの演習とこれまでの総復習
◯ 国公立と私立の過去問演習サイクル
◯ 入試レベルまでまだ始められなければ基礎を完成させる
夏休み
◯ 二次試験で使う科目の基礎の完成
◯ 共通テストしか使わない科目毎日30分
ここから4つの時期それぞれについて詳しく見ていきます。
夏休み
夏休み期間(8月末まで)は、まとまった学習時間を確保しやすく、複数の科目を並行して進める絶好のチャンスです。
優先順位はまず数学、次に英語と理科が重要です。大学によっては二次試験で国語が課される場合もあるため、二次試験で使う科目を中心に対策を進めましょう。
共通テストのみで使う科目も、毎日30分から1時間程度は継続することが効果的です。
また、科目ごとに割く学習時間は、共通テストと二次試験の配点を参考に優先順位を決め、特に配点が高い科目にはより多くの時間をあてるようにしてください。
数学
数学の学習では、まずIA・IIB・Cの典型的な解法をほぼ確実に解けるようになることが最重要です。
青チャートの「コンパス3」までの問題は、80%程度はスムーズに解ける状態が望ましく、レジェンドやフォーカスゴールドなどでも同様です。
共通テストやセンター試験の過去問を時間制限なしで解き、65点程度取れるかどうかで実力を判断します。各大問(2)までが典型問題となっているため、ここまで解けているかどうかをチェックします。
次の段階では、IA・IIB・Cの入試レベルの問題と、数学IIIの典型的な解法が網羅されているかが焦点です。
文系数学は志望校の過去問を解き、二次試験で70%以上取るためにより難しい問題が必要な場合は、プラチカや標準問題精講、良問問題集、1対1対応の演習などの難問対策教材に取り組み始めます。
数学IIIに関しては、青チャートなどの網羅型問題集のコンパス3までを抜け漏れなくスラスラ解けることが目標です。その段階をクリアしていれば過去問に取り組み、難易度の高い問題が求められる場合はプラチカや難しい問題集へ進みましょう。
英語
英語は、まず一文読解の力を徹底的に固めることが最優先です。
一文読解とは、英単語・英熟語・英文法・英文解釈を指し、これらがしっかり身についていれば、共通テストでは時間制限を設けなければ85%前後の得点が可能で、中堅私大の合格ラインにも十分達するレベルです。
英単語については、単語帳の最難関レベル以外で、1,500〜1,600語程度までを確実に覚えることを目指します。最難関単語は後回しでも構いません。
英熟語については、特に最重要となる600語ほど、特に動詞の熟語を優先して覚えましょう。
単語・熟語は、95%の正答率を1秒以内で答えられるレベルまで仕上げることが目標です。
英文法は、既に基本的な構造の理解が終わっている前提で、Vintageなどの文法問題集を利用し、500問程度をスムーズに説明できる水準まで、90%程度の完成を目指します。語法についても熟語同様に仕上げましょう。
英文解釈は標準レベルのテキスト(基礎英文のテオリア、Rise1、基礎100、英文熟考、入門英文問題精講など)を2〜3周こなして、しっかり内容を理解できる状態にしておきます。
この一文読解が仕上がったら、次に進めたいのが長文読解と英作文です。
長文読解は、週に2〜3題解いて復習し、音読も行うことが効果的です。おすすめはRulesシリーズで、1冊に12問収録されており、2〜3周してから次のレベルに進みましょう。10月ごろまでに最低でもRules3まで仕上げることを目標にします。
英作文については、まず和文英訳からスタートします。英文のテンプレート(100文程度)を暗唱することで、典型的な英作文ができるようになります(ハイパートレーニングがおすすめです)。
続けて自由英作文でも、60語以上の構成パターン(例:結論→理由→具体例1→具体例2)を学習し、同じくハイパートレーニング自由英作文編で練習します。
まとめると、まずは一文読解を徹底的に固め、その後長文読解へ、さらに余裕があれば英作文にも取り組みましょう。
化学
化学の学習では、まず理論化学の典型問題を自力でスラスラ解けるようになることが最優先です。
セミナーやリードα、新標準演習、新基本演習などの基本問題までしっかり理解し、解ける状態になれば、共通テストやセンター試験の理論分野でおおよそ65%程度の得点が期待できます。また、中堅私立大学レベルは合格点に到達する可能性も十分あります。
この基礎ができたら、理論化学の応用問題と、無機・有機・高分子それぞれの典型レベルを同時並行で進めます。
理論化学の応用については、(セミナー、リードα、新標準演習)の発展応用問題や重要問題集、鎌田の化学問題集などを使い、一問ずつ丁寧に解きながら、解法パターンや忘れがちな公式・化学式もその都度復習して定着させていきましょう。
無機・有機・高分子分野については、まずは反応式や構造式を暗記できるかが大きなポイントです。
一度に深くやり込むよりも、1週間の中で頻繁に何度も繰り返し目を通し、知識を長期記憶に残す戦略がおすすめです。
これらの分野は、見て覚えるよりも「実際に書いて覚える」学習法が効果的です。自分で手を動かして書き写したり、白紙に再現するなど、反復することで定着しやすくなります。
もしどの分野を進めればいいかに迷ったら、センター試験や共通テストの過去問を大問ごとに解いてみると、得意・不得意分野の分析ができます。
過去問の得点から、二次試験や私立大学入試でもどの程度得点できるかのおおよその目安になります。
物理
物理のは、各分野ごとに仕組みの理解 ⇨ 典型解法の習得 ⇨ 応用問題への挑戦というステップで進めていきます。
まずは力学から始め、基本的な仕組みの理解と典型的な解法をしっかり身につけることを最優先しましょう。
各分野ごとに、講義形式の参考書と典型問題集を併用します。
講義系テキストは複数ありますが、その中から自分に合った1冊を選び、あわせて典型問題集として「セミナー」や「リードα」の基本問題、あるいは「物理のエッセンス」を使います。
セミナーやリードαは典型問題を網羅しており、学習量は多いものの着実な力がつきます。一方、エッセンスは代表的な問題が厳選されていて効率良く学習できますが、基礎が十分でないと少し難しく感じやすい側面もあります。
どちらを選ぶ場合でも、セミナーやリードαは基本問題まで、エッセンスなら全問をスラスラ解ける状態になることが目標です。
全分野の基本を自力で解けるようになったら、「良問の風」でワンランク上の応用問題に取り組むのがおすすめです。
良問の風はやや難易度の高い問題が多く、これをしっかり解けるようになれば、旧帝大レベルの入試でも(2)まで十分対応できる力が身につきます。
なお、「重要問題集」や「名問の森」はかなり難易度の高い問題集なので、まずは「良問の風」を優先し、しっかり解けるようになってからステップアップするのが効果的です。
生物
生物では、まず基礎レベルの知識を幅広く身につけることを最優先とします。
「セミナー」や「リードα」といった問題集の基本問題までを、9割程度確実に解ききることを目標に進めましょう。
これに加え、教科書・資料集・講義系の参考書を組み合わせて、基礎知識・計算問題・簡単な記述問題を網羅的に学び、知識を定着させていくことが大切です。問題集は何周も繰り返し解いて、内容を長期記憶に残す戦略で進めてください。
もし基本問題までスラスラ解けるようになったら、より発展的な難関問題集に順次取り組み、実践力を養っていきます。難関問題集に並行して、これまで使ってきた教材の内容も総復習し、知識の穴を埋めることを心がけましょう。このように基礎から発展まで段階的に進めることで、入試本番で必要な得点力が身につきます。
共通テストでしか使わない科目である国語、社会、情報については、夏休み中に重点的に学習時間を確保することをおすすめします。
国語
国語では、まず古文単語(およそ300個程度)や基本文法を優先して仕上げることが優先です。
古文文法の問題演習で理解が深まったら、漢文に進みます。
漢文は代表的な句形・句法(例:漢文ヤマのヤマなどで60個程度)が目安となります。
社会
社会科目については、集中講義シリーズなど1冊に絞った教材で知識を整理するのが効果的です。
2025年から共通テストの社会は大幅な再編があり、必要な知識量が大きく減っています。
そのため、まずは最新の共通テスト過去問にしっかり目を通し、出題傾向や知識レベルを把握したうえで、必要最小限の内容を重点的に学習していきましょう。
情報
情報対策には、参考書を1冊使い、実戦問題集で演習します。
おすすめは「きめる!共通テスト 情報Ⅰ」や「高校の情報Ⅰが1冊でしっかりわかる問題集」などで、どちらか1冊を通して基礎的な内容を理解して実戦問題集を繰り返して復習します。
どの科目も夏休みにできる限り時間をあてたいところですが、英語・数学・理科が入試対策としては優先度が高いため、共通テストのみ使用する科目は“毎日1科目30分程度”と学習時間を決めて、ローテーション形式で繰り返し学ぶことが大切です。
暗記が中心となる科目は、30分間で昨日の復習と新しい範囲をバランスよく回し、長期記憶に定着させることを意識して進めましょう。
9月から11月末
9月から11月末にかけては、次の3つのテーマを柱にを進めます。
◯ 二次試験や私立大学入試で使用する科目の入試レベル演習と総復習
◯ 国公立大学二次試験および私立大学の過去問演習
◯ まだ入試レベルの問題に取り組めていない場合は基礎固めの徹底
12月の第1週からは共通テスト対策が中心となるため、二次試験レベルの演習や過去問演習は11月末までにできる限り進めておきたいです。
各科目については、夏休み中に取り組んだ内容を引き続き順番に進めます。
共通テストやセンター試験の過去問を解いて最低でも70%程度取れるようになれば、典型的な問題には十分対応できていると考えられます。
次のステップとして、MARCH・関関同立レベルの過去問を解いて、この段階で65%程度得点できるようであれば、いよいよ難関国公立大学の過去問にもチャレンジする実力がついてきたと判断できます。
得意科目は週に1年分の過去問を解きしっかり復習、苦手科目については定期的にセンターやMARCH・関関同立の過去問を演習しながら、自分の得意・不得意をリストアップし、継続的に総復習を進めましょう。
まとめてみましょう。
◯ 夏休みに完成させた標準レベルをさらに強化
◯ センター・共通テスト過去問で70%以上を目指す
◯ 入試レベルの問題集にも取り組む(難関問題集の活用)
◯ MARCH・関関同立の過去問で実力チェック
◯ 二次試験の過去問にも挑戦
理想としては、11月末までに二次試験の過去問を合計10年分解き終えることを目標としましょう。
12月第1週から共通テスト本番
12月第1週からは、勉強時間の8〜9割を共通テスト対策に充て、残りの1〜2割を二次試験の過去問演習とその復習に使う配分に切り替えます。
英語・数学・理科2科目は、実戦問題集で共通テスト本番の形式にしっかり慣れることを重視します。
特に今年度から出題傾向が大きく変化しているため、過去問よりも秋に発売される最新の実戦問題集に優先して取り組むのがおすすめです。
国語・社会・情報は、この時期にもう一度知識のインプットを再開しましょう。
現代文では漢字や慣用句、余裕があれば重要キーワードにも目を通します。古文は古文単語300語と文法、漢文は「ヤマのヤマ」を使って代表的な句形・句法60個をしっかり覚えるのが目標です。
社会と情報に関しては、参考書1冊を使って全体の知識を一通り復習します。
12月後半からは実戦問題集に取り組み、アウトプットを通じて得点力の仕上げに入りましょう。
④共通テストから二次試験
1月中旬に共通テストが終了し、2月25日に二次試験が行われます。
2月1日から10日ごろまでは私立大学の入試期間となります。
過去問演習については、学部によって3年分だけ解く場合もあれば、10年分取り組む場合もあります。いずれにしても、過去問を解くだけでなく、復習や分析をしっかり行いましょう。
私立大学の受験期間中以外の時間は、二次試験の過去問演習と総復習に充てます。
イクスタの創業者、土井による論理的・戦略的な受験計画と戦略の作成
過去問に入る時期や基礎完成の時期などいつ何をやればいいか、完全にコントロールできるようになる必要があります。

> 論理的で抜け漏れのない受験計画の立て方が分かる イクスタコーチ
時期別対策




