【現代文のアクセス】レベル・問題数・特徴|共通テストから早稲田の現代文まで対策



こんにちは。早稲田大学 教育学部 社会学科出身、イクスタコーチの土井です!
今回は入試現代文へのアクセスシリーズについて特徴から難易度、使い方まで詳細に説明していきます。大多数の受験生にとってアクセスを使うとしたら基本編なので今回はこちらを中心にご紹介していきますね!
田村の現代文と並び、大学受験を始めたばかりの受験生がまず使う現代文の参考書のうちの一つです。
入試現代文へのアクセスの基本情報
出版社
河合出版
価格
いずれも¥933円+税
難易度
★★☆☆☆(基本編)
★★★★☆(発展編)
★★★★★(完成編)
当社イクスタでは広告記事や販売促進のために参考書レビューをすることはありません。すべて受験生に平等な情報をお伝えするための本音だけの記事です。
入試現代文へのアクセスとは??
アクセスは、数ある現代文の参考書の中でも丁寧な解説に定評のあり、イクスタコーチの受講生にもおすすめすることの多い人気参考書です。文系のみならず、共通テストで国語を使用する理系にも向いています。
近年のイクスタコーチ受講生では 青山学院大学総合文化政策学部、明治大学商学部に合格した受験生がアクセスシリーズを使用していました。
基本編、発展編、完成編というようにレベル別に分かれているため、個々の受験生は自分に合ったものを選ぶことができますし、一冊終わったら次のレベル、というふうに段階的に進められるのも魅力です。例題と練習問題に分かれており、順を踏んで学習できます。
入試現代文へのアクセスのレベル
入試現代文へのアクセス3冊のレベル
基本編は、MARCHレベルの大学を志望する受験生に向いています。国語に苦手意識がある人はとりあえず基本編から始めることをおすすめします。大学受験の現代文対策はまだやったことがない場合にはまずこの参考書から始めましょう!文章読解の基本が集約されており、簡潔に重要なポイントを学ぶことができます。
発展編は、早慶上智レベルの受験生が演習のために使うのがおすすめの使い方です。基本編と異なり単語や文章がかなり難しくなりますので、入試問題演習として使用するのに適しています。
完成編は、早慶、それに旧帝大を志望する人に適しています。模試や入試本番前に解いておくと難しい文章を読解するポイントが見えてくるでしょう。
発展編からはかなり難しいので現代文が苦手な場合は基本編から手をつけてください。
共通テストの現代文で言えば、基本編は国語が苦手・現代文をこれから始める全受験者向きです。
発展編は、共通テストレベルは100点中60〜70点は取れて、さらに得点を伸ばしたいというレベルが最適です。
完成編は、すでに80〜90点取ることができ、読みを正確にして満点近くを狙いたい人が挑戦すべきです。
入試現代文へのアクセスの特徴

続いて、入試現代文へのアクセスシリーズの特徴について詳しくご紹介していきますね。
「読解へのアクセス」はシンプルなようで見落としがちな重要な技術です
一番の特徴は解説の丁寧さ
入試現代文へのアクセスは、なんといっても解説が丁寧なのが長所です。
要点と答えの理由を簡単に解説して終わり、という現代文の参考書もたくさんありますが、アクセスはそうではありません。まずは文章そのものの内容をしっかり理解することから始めてくれます。
文章の内容まで丁寧に解説してくれる
まず、文章の解説がとても充実しています。各段落が何を述べようとしているのか、というマクロな視点から、ここの指示語は何を指しているのか、これは何のたとえなのかというミクロな箇所まで余すところなく説明されています。
この解説を一通り読めばある程度難解な文章でもしっかり理解出来るはずです。それに加えて簡潔な要約も載っており、大意把握にも困りません。
設問の解説も丁寧!
文章の解説の他には、当然設問の解説もついています。選択肢の問題であればなぜこの選択肢が正解でこれが誤りなのかを丁寧に説明してくれますし、抽象的なテクニックとして「こういうふうに読むと良い」という方針が明瞭に説明されており、広く役立つ力が身につきます。
解けない問題があったときは、解説を読むことでなぜそれが答えになるのか、そしてこういう問題はどういうアプローチをすればいいのかが理解出来るはずです。
また、文章に登場した難しい単語をまとめてピックアップしてあるため、現代文読解に必要な語彙を学ぶことが可能です。
「読解へのアクセス」という現代文を読む際の技術・技法が簡潔にまとまっているので、何ができればいいのかが分かりやすいですよ!
入試現代文へのアクセスの使い方

次に入試現代文へのアクセスの使い方についてご紹介していきます。
問題を解く際の全般的な注意
現代文の問題を解くときは答えだけでなくそれに至る論理が欠かせません。
文章を読んで「なんとなく」で作った・選んだ答えはポイントを抑えられていないことや余計な内容が含まれていることが非常に多く、それは得点に結びつきません。
文章を読むときは大切だと感じた箇所に傍線を引いたり、接続語をマルで囲んだり、実際の試験同様の作業をするのが大切です。英語の長文と同じく、文章を読む際には問題文に印や線をたくさんつけることができると、素早く解答を終えることができます。
また記述問題であれば要点をメモして整理してから答案を清書するのが良いでしょう。ノートを作成し、答えだけでなくそうしたメモ等も詳しく書いておく習慣をつけましょう。
選択肢の場合は自分が選んだ選択肢が正しい理由、さらに他の選択肢が不適切である理由をよく考える癖をつけましょう。選択肢の問題は特に「なんとなく」で選びがちなので要注意です。「なんとなく」で選択肢を選んでも難関大学には対応できません。
現代文は「なんとなく」答えを選択できる科目なので危険です。志望校の入試問題で合格点を取れるレベルまではるか遠いのに、「自分は苦手じゃない」と勘違いしてしまうパターンも。
例題の使い方
本編の最後に読解へのアクセスの一覧表があります。これは現代文をやればやるほどじわじわと良さが分かってくる優れもの。
例題は簡単な問題なので、手応えを感じにくいところもありますが、読解へのアクセスの1-6はどんな現代文で使える、深い技術なので必ずマスターできるように意識してください。
例題の問題文と設問自体は必要ないと思えば取り組まなくても結構ですが、国語に苦手意識を持っていたり、出来る限り多くの題材に触れたいと思っていたりする受験生は例題にも是非取り組んでみましょう!
問題は必ず解いてから解説を見よう
ただし、ただ文章を読んで解説を読むのはNGです。国語の問題は解説を読むと、なんだかわかりきった気分になってしまうことがよくあります。
しかし、実際の試験ではノーヒントで自分で読解しなければならないのです。解答解説を読むだけでは、読解のコツが定着していることは滅多にありません。
かならずノートを用意して、実際に問題を解いてみましょう。読んでいるのみだと効果がほとんどありません。
例題を解いたら答え合わせをします。自分で導いた答えが間違っていたら、正解を知るだけでなく、解説を読んで自分の思考のどこが間違っていたのかチェックするのです。
自分の癖や傾向を見抜くことが実力向上への最大のコツです。解説を読み、間違えた原因の分析が終了したら、いざ練習問題へ。
練習問題は入試だと思って解こう!
練習問題は、例題で把握した自分の癖に注意しつつ文章を読みましょう!
傍線を引くなどの工夫はもちろん行ってください。試験本番と同じだと思って、相応の意気込みで臨むのが大切です。
時間設定を気にするかもしれませんが、初めのうちは(正解率が安定しないうちは)長時間かかってしまっても構わないので、自分の納得がいくまで丁寧に文章を読んで、「これだ!」と思える答えを選びましょう。
時間に追われて回答すると、どうしても読解が浅くなり、学習効果が得られないのです。
解答の過程・論理を復習しよう!
一通り解いたら答え合わせをします。択一問題では、どういう理由でこの選択肢が正解で他が誤りなのか丁寧に読みます。
記述問題では必ず述べなければならないポイントは何で、それは文章のどこにあるのかをよく振り返りましょう。答えを見て終わり、ではほとんど意味がありません。そこに至るまでの過程・論理を最大限吸収するよう努めてください。
最後のまとめ「読解へのアクセス」一覧表
現代文は感覚で入試レベルでも得点できてしまう人が受験生の10%ほどいるのは事実です。一方で現代文は感覚だと思い込んでいると参考書から吸収すべきものが吸収できなくなるので注意してください。
感覚でも読めるし、たくさん読めば勘も身についてきてゆっくりですが実力も伸びます。でも、不安定です。
不安的ではなく安定した現代文の力を身につけるには、確実な知識と技術が必要です。その技術は何かというと本文の解説で何度も出てきて、この参考書の最後のにもまとまっている「読解へのアクセス」なんですね。
私は現代文がとても得意で、早稲田模試でも現代文は上位10%に入っていましたし、高2の段階で学校の授業で取り扱った東大の問題も解けたりしていました。そんな私からみてもこの参考書にまとまっている「読解へのアクセス」は非常に良くできていると感じます。
感覚や勘で現代文を読んで、ある程度点数が取れている人が改めて「読解へのアクセス」を確認して自分の読み方を言語化することで、文章の解像度が格段に上がるでしょう。
アクセスと同時に伸ばしたい現代文の力
ここまでご紹介してきたように現代文のアクセスでは、現代文を読むための明確な知識や技術を手に入れることができます。現代文のMARCH以上の難関大学で合格点を取るためには、アクセスで学ぶこと以外にもやるべきことがあります。
一つ目は漢字です。漢字は絶対に完璧にしてください。現代文だけでなく大学入試で使う科目の中でも最も得点期待値の高い科目です。覚えれば絶対に得点できるようになる分野は大学受験においてはほとんどありません。それだけお得なんですね。漢字は必ず入試までには完璧と言っていいほどに仕上げてください。
二つ目は現代文用語・キーワードです。逆説(逆接ではないですよ)、形而上学、などのキーワードは現代文で頻出です。知識として知っているか知らないかでその文章の読解できる程度に大きく差がついてしまいます。1冊でいいので現代文頻出の用語やキーワードを学んでください。
現代文の勉強方法について、私の予備校時代の後輩で早稲田に合格した後輩がとても良い現代文の勉強法についてご紹介しています。こちらもご参考にしてください!
参考:【現代文】センスがなくても0から難関大合格まで点数を上げるための勉強法と使う参考書 - イクスタ
この記事の冒頭でもご紹介した、明治の商学部に合格した2021年のイクスタコーチ受講生もアクセスを使っていました。現代文だけでなく国語の勉強法をご紹介しているのでこちらもご参考に!
参考:【明治の国語】5月に文転した僕が明治の過去問で8割取れるようになった勉強法と参考書 - イクスタ
現代文の勉強法を間違えないためのおすすめの動画
再生できない場合はこちらから!
Youtubeで再生する


| ことばはちからダ!現代文キーワード | |
| 必須キーワードを復習 | |
| おすすめ度 | 8.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜40点 |
| 価格 | ¥902 |
| 購入 | Amazon |

| 読解を深める 現代文単語 | |
| 主要キーワードをおさらい | |
| おすすめ度 | 7.5/10 |
| レベル | 共通テスト:〜50点 |
| 価格 | ¥935 |
| 購入 | Amazon |

| 生きる現代文キーワード | |
| 主要キーワードを解説 | |
| おすすめ度 | 8.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜60点 |
| 価格 | ¥1,023 |
| 購入 | Amazon |
| 生きる現代文キーワード(駿台文庫)の使い方・レベル・タイミングは?どの志望校におすすめ? - イクスタ | |

| 現代文キーワード読解 | |
| 難関大レベルのキーワード | |
| おすすめ度 | 8.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜60点 |
| 価格 | ¥990 |
| 購入 | Amazon |
| 現代文独特の表現を覚えよう!「Z会現代文キーワード読解」の特徴や使い方は? - イクスタ | |

| 新国語総合ガイド | |
| 重要キーワードをおさらい | |
| おすすめ度 | 5.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜50点 |
| 価格 | ¥1,470 |
| 購入 | Amazon |

| 漢字マスター1800 | |
| 漢字はどれか1冊 | |
| おすすめ度 | 7.5/10 |
| レベル | 共通テスト:〜60点 |
| 価格 | ¥900 |
| 購入 | Amazon |
| 入試に出てくる漢字を制覇しよう!入試漢字マスター1800+の特徴や使い方を教えます - イクスタ | |

| 田村のやさしく語る現代文 | |
| 現代文とは何かから解説 | |
| おすすめ度 | 8.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜40点 |
| 価格 | ¥880 |
| 購入 | Amazon |
| 現代文が苦手なあなたはここから。田村のやさしく語る現代文のレベルや使い方 - イクスタ | |
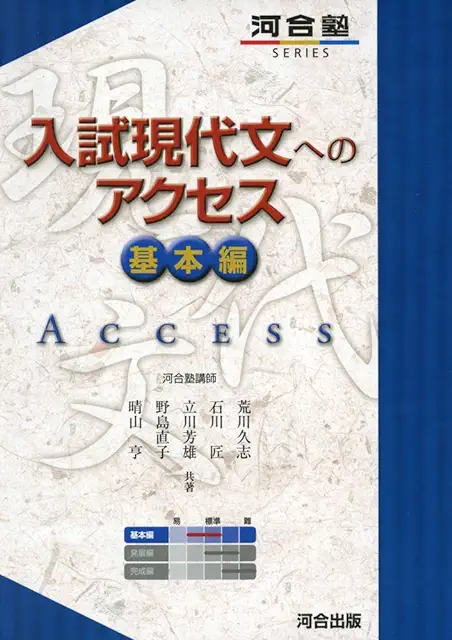
| 入試現代文へのアクセス 基本編 | |
| 標準的な解き方の型 | |
| おすすめ度 | 8.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜50点 |
| 価格 | ¥1,026 |
| 購入 | Amazon |
| 現代文へのアクセスで合格レベルまで伸ばす方法 共通テストから早稲田の現代文まで対応!【レベル・問題数・時期】 - イクスタ | |

| 入試現代文へのアクセス 発展編 | |
| 中堅レベルの問題演習 | |
| おすすめ度 | 7.5/10 |
| レベル | 共通テスト:30〜70点 |
| 価格 | ¥1,026 |
| 購入 | Amazon |

| 現代文読解力の開発講座 | |
| 標準〜難関レベルを深く解説 | |
| おすすめ度 | 8.5/10 |
| レベル | 共通テスト:50〜80点 |
| 価格 | ¥1,320 |
| 購入 | Amazon |

| 現代文と格闘する | |
| 最難関レベルの記述対策 | |
| おすすめ度 | 8.0/10 |
| レベル | 共通テスト:70〜90点 |
| 価格 | ¥1,416 |
| 購入 | Amazon |

| 現代文 標準問題精講 | |
| 最難関レベルの記述対策 | |
| おすすめ度 | 8.5/10 |
| レベル | 共通テスト:70〜90点 |
| 価格 | ¥1,430 |
| 購入 | Amazon |
イクスタとは
イクスタとはYouflex株式会社の土井万智(どいまさと)がほぼ1人で運営する、はじめての大学受験を成功させるためのプラットフォームです。普通に予備校にいって普通に勉強するだけでは難関大学に合格できないという現実を、どう打破するか。第一志望に合格する15%に入るためには、どう違いを作るか。毎年、1年間一人一人の受験生に毎週の面談で密着すると、実際の事実と世間で理解されている情報の乖離がある。このビジョンをもとに、Webの記事、Youtube動画、書籍、オンラインコーチングという4つの柱で独学の受験生を支援します。
イクスタの創業者、土井による論理的・戦略的な受験計画と戦略の作成
過去問に入る時期や基礎完成の時期などいつ何をやればいいか、完全にコントロールできるようになる必要があります。

> 論理的で抜け漏れのない受験計画の立て方が分かる イクスタコーチ
国語概論















 英語の勉強法
英語の勉強法 数学の勉強法
数学の勉強法 現代文の勉強法
現代文の勉強法 古文の勉強法
古文の勉強法 化学の勉強法
化学の勉強法 物理の勉強法
物理の勉強法 世界史の勉強法
世界史の勉強法 英語の参考書
英語の参考書 数学の参考書
数学の参考書 現代文の参考書
現代文の参考書 古文の参考書
古文の参考書 化学の参考書
化学の参考書 物理の参考書
物理の参考書 日本史の参考書
日本史の参考書 世界史の参考書
世界史の参考書 土井の受験攻略本
土井の受験攻略本 Youtubeチャンネル
Youtubeチャンネル 受験カレンダー
受験カレンダー コーチング
コーチング