【日本史】10ヶ月で明治大学に合格した日本史の逆転勉強法と参考書を徹底紹介!

こんにちは〜
明治大学商学部のダイキです。
先日、某カフェでバイトの面接を受けてきました。実は自分、人外が喋るテーマパークのキャストと某予備校のチューターの採用面接に計2回落ちています。貯金も底を突きかけているので、もう必死でした。そこで、受験期に勉強で集中するためにしばしばそのカフェを利用していて、落ち着いた雰囲気が好きだという事をアピールし、さらにそこのコーヒーが大好きだったと伝えました。僕の話し方やわざと作った表情の明るさも相まって、面接官の人は思わずニッコリ。見事に好印象を与えることができました。採用の連絡を心待ちにしています。
※因みにそこのコーヒーは一回しか飲んだことがありませんし、そのカフェで勉強するときはほとんど毎回何も注文せずにテーブルだけ使ってました。極力出費を減らし、受験勉強のための養分を上手く得ていた過去の自分を褒めてあげたいですね!
自分は高校三年の時に文転し、5月から受験勉強を本格的に始めて、明治大学商学部・政治経済学部に合格する事ができました。受験勉強を始める前までは日本史や国語の高校での範囲はほぼ0からのスタートでした。高校もクラスの20%くらいしか一般受験しないので大学受験の知識もほぼなく、5月の駿台共通テスト模試で偏差値45くらいだった気がします。
明治でも平均80%取れるようになった日本史の勉強法
そこから今回ご紹介する勉強を始めて、日本史は明治の商学部では最高85%(4年間の平均81%)、明治の政治経済学部では最高81%、早稲田の社会科学部でも最高72%を取ることができました。

今回は、私大の日本史対策で筆者が受験生の時に使っていたおすすめの参考書、教科書と勉強法を紹介していきます。高3の4月から始める想定で説明しようと思います。
(1)通史→(2)文化史→(3)その他補助教材、問題集→(4)過去問
まず日本史を勉強するには通史から入っていきましょう。通史とは歴史上での出来事の流れのことですね。
(1)通史のおすすめの参考書、教科書の順番
○金谷の「なぜ」と「流れ」がわかる本
↓
○スタディサプリor石川の日本史B講義の実況中継
↓
○教科書(詳説日本史)
○金谷の「なぜ」と「流れ」がわかる本

いちばん最初に日本史の勉強に取り掛かる人は、まずこれを使うのがおすすめです。歴史の大まかな流れが分かりやすく講義形式で整理されており、出来事と人物が関連づけて書かれているので、歴史の流れが掴みやすくなっています。まずこれを読み基礎を固めを作り、後からより具体的な知識をインプットしていきましょう。3周くらいすれば良いかと思います。
おすすめの時期
4月〜5月
○スタディサプリ

独学の受験勉強を支えるにはもってこいのスマホアプリです。講師の伊藤賀一先生の講義は、教科書や参考書では説明してくれない歴史上の出来事の具体的な背景の説明などを多く話してくれるので結構面白いです。頭に入ってきやすいですよ。
テキストを自分で印刷し、講義の内容のメモ(どこでメモを取るべきかは動画内で指示してくれます。)を取りながら進めましょう。あと、全ての講義をクソ真面目に1倍速で見ていると時間がかかって仕方ないので、自分の聞き取れる範囲内で再生速度を速めるのが良いですよ。もちろんですが、テキストで定期的に復習しましょうね。
復習のタイミングは1日後、1週間後、1ヶ月後にそれぞれ行うのが良いと言われてます。エビングハウスの忘却曲線というやつですね。赤本手帳などを活用して復習タイミングを逃さないようにしましょうね。
もし講義を進めるならば、ハイレベル&トップレベルを見るべきでしょう。スタンダードに比べ私大受験に必要な知識が多く紹介されてます。
また、金谷の「なぜ」と「流れ」の次はこれか実況中継かのどちらか一方を使いましょう。自分の好みの方を使うと良いです。両方やるのは量が重すぎると思うので、おすすめしません。
おすすめの時期
5月〜10月
○石川の日本史B講義の実況中継
スタディサプリ同様、より詳しく通史について学ぶのに必要です。教科書の硬めな文章やレイアウトが苦手だと感じる人におすすめですよ。入試において重要な出来事の流れと背景を分かりやすく書いているので、効率よく勉強できます。付属のサブノートがあるので、それを中心に復習を進めると良いでしょう。
1.まず講義を読みつつサブノートにメモを書き込む
2.翌日次の講義を読み進めながらサブノートにメモを書き込み、前日のサブノートで復習。
このサイクルを繰り返しながら勉強を進めましょう。全部で4冊あるため少し大変ですが、頑張って最低でも3周することをすすめます。
また、入試頻出の史料を取り上げているので、疎かにされがちな史料問題対策にもなります。より史料問題の対策に力を入れる必要がある人は、この記事にある(3)その他の補助教材を参考にしてみてください。
おすすめの時期
5月〜10月
○教科書(詳説日本史)

通史の仕上げは教科書でやるのがおすすめです。ある程度通史の知識が固まってきた頃に教科書を読めば、知識が少ない状態で読むよりも文章の理解度が大きく変わってきます。特に教科書の中でも、山川出版社の詳説日本史という教科書がいちばん良いと思います。なぜなら、日本の大学の受験生の大半がこれを使っていて、入試問題もこの教科書をベースにつくられていることが多いからです。ただ、書かれている内容にそれほど違いはないので、別の教科書を持っている人はそれでも大丈夫です。
ちなみに早稲田の日本史でも、教科書の文から丸々抜粋してあるような問題が多くあります。大学側が受験生に向けて教科書の内容理解を求めているのがよく分かりますね。
おすすめの時期
10月〜受験終わりまで
(2)文化史の勉強法
○教科書
先ほど紹介した山川の教科書です。
○資料集

学校で副教材として配られる資料集です。図表みたいな呼ばれ方をすることもあります。
文化史は通史と比べ疎かにされがちな範囲です。実は自分も、文化史の比重を軽めにして勉強を進めてしまったため、早稲田の試験本番でも、早稲田志望なら正解するべき問題を落としてしまいました。大学受験では、こうした簡単な間違いで不合格になってしまうこともあります。こういうことになってしまわないように、皆さんは自分の受験する大学や学部の問題傾向を過去問を通してしっかり把握し、勉強量の配分を間違えないようにしましょう。
文化史を勉強する上で大切なのは、どの作品がどの時代のものなのかを整理して頭に入れておくことです。画像と名前をセットで勉強すると覚えやすくなるので、資料集と教科書を併用するのがおすすめです。ひたすら暗記の作業ですね。資料集を持っていない人は買っておくべきだと思います。
おすすめの時期
10月〜受験終わりまで
(3)その他日本史の補助教材
○東進日本史B一問一答
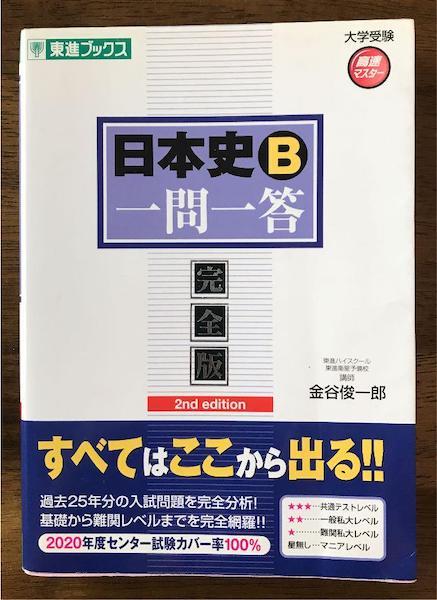
一問一答の参考書は、私大の受験生みんなが使っているイメージがあると思います。確かにこれを極められればかなりの高得点を期待できますが、使い方には要注意です。というのは、通史の知識が固まっていないうちに使うと効果が薄いということです。この参考書だけでは歴史の流れが掴みにくいんですね。
ですから、これを本格的に使い始めるのは通史がある程度固まる11月ごろから始めるのが良いでしょう。ちなみに僕は過去問を解いたのちにあやふやなところが出てきたら一問一答に直接書き込んだりして知識を整理し直してました。
おすすめの時期
10月〜受験終わりまで
○東進日本史史料一問一答
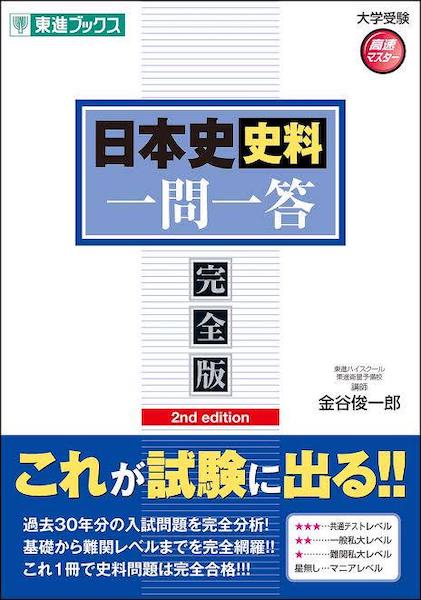
受ける大学や学部によっては、史料が頻出のところもあります。その対策に使うと良いのがこの参考書です。ここ数年の過去問を解いて、どの時代の史料がよく出るのかなどを確認し、その部分をピンポイントで対策するのもおすすめです。
おすすめの時期
10月〜受験終わりまで
○実力をつける日本史100
アウトプット用の問題集です。通史問題が75問、テーマ別問題(交通史、商業史など)が25問、論述問題が5問で構成されていて、少し問題の難易度が高いのが特徴です。
早慶レベルのコアな知識が必要になる問題が結構あるので、もう少し基礎を固めたいと思った人は東進の日本史問題集完全版などもう少し難易度の低いものをお勧めします。
通史が定着し始める11月ごろから使うのが良いと思います。ちなみに私大受験であれば、論述問題はやらなくても良いと思います。論述問題は200字とかです。余裕がある人はやってみても良いかもしれません。
おすすめの時期
11月〜受験終わりまで
○日本史用語集
忘れてしまった語彙の意味などを辞書で引くように使うのが良いと思います。結構便利です。人によっては、知識の整理として最初から最後まで読み進めるといった使い方が自分に合っているという人もいます。自分もその使い方をしていましたが、今振り返ると情報量が多すぎてやや読み進めにくかったです。自分に適した使い方をしましょう。
おすすめの時期
通年
○元祖日本史の年代暗記法
その名の通り年代暗記をするのに使います。z語呂で覚えるように作られていますが、繰り返し眺めているうちにそのまま覚えられることもあります。)
何か出来事が起こった西暦をそのまま問題に出す大学や、出来事の順番を答えさせる大学が中にはあるので、そういう大学を受ける人にとって最適な参考書と言えるでしょう。
おすすめの時期
10月〜受験終わりまで
(4)過去問
日本史の過去問演習ですが、他の科目の試験に比べそこまで時間がかからないことが多いかと思います。ですから、解き終わった時の見直しの練習等もしておくと良いかもしれません。見直し抜きで終わらせると、意外とケアレスミスが見つかることが多いです。試験のときだけでなく、過去問演習のときから見直しを癖づけでおくだけでも本番でのミスは格段に減ることでしょう。
問題を解き採点し終わったら、間違えたところの時代背景や用語の復習をしておきましょう。一つ知識が抜けていると、それに関連する別の知識の抜け漏れがあることが結構あるからです。
また、自分で間違いノートを作ってまとめてみたり、一問一答の参考書にメモを書き込んで知識の整理をし直すのも良いでしょう。それをこまめに読み直すことで苦手を潰すことになりますし、自分の場合は試験本番の時に会場に持って行って休み時間に見直し、今までの自分の勉強量を再確認できたことで自信にもつながりました。
※(3)その他の補助教材の○東進日本史B一問一答を参照
明治に合格するために届けたいこの想い
僕が明治に合格するまでに学んだ他のノウハウもぜひ参考にしてください!
> 【明治の国語】5月に文転した僕が明治の過去問で8割取れるようになった勉強法と参考書 - イクスタ
> E判定から約10ヶ月で明治に逆転合格、Marchほぼ全勝した自分が、これから受験英語を本気で始める人にすすめる参考書と勉強法 - イクスタ
日本史の勉強法を間違えないためのおすすめの動画
再生できない場合はこちらから!
Youtubeで再生する


| 金谷の「なぜ」と「流れ」がわかる本シリーズ(東進ブックス) | |
| 最重要の仕組みを図で整理 | |
| おすすめ度 | 8.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜60点 |
| 価格 | ¥1,320 |
| 購入 | Amazon |
| 日本史の木の幹を立てる。東進「金谷の日本史 なぜと流れがわかる本」を使って基礎を固める勉強法 - イクスタ | |

| 日本史探究授業の実況中継シリーズ | |
| ゼロから最難関レベルまで4冊で網羅 | |
| おすすめ度 | 8.5/10 |
| レベル | 共通テスト:〜90点 |
| 価格 | ¥1,540 |
| 購入 | Amazon |
| 【日本史】独学で通史を勉強し、早慶MARCH関関同立を目指すなら実況中継をやりこめ! - イクスタ | |

| ナビゲーター日本史シリーズ | |
| ゼロから中堅レベルまで4冊で網羅 | |
| おすすめ度 | 6.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜75点 |
| 価格 | ¥1,100 |
| 購入 | Amazon |

| 詳説 日本史探求 | |
| 最もメジャーな教科書 共テの中心 | |
| おすすめ度 | 7.5/10 |
| レベル | 共通テスト:〜60点 |
| 価格 | ¥900 |
| 購入 | Amazon |
| 日本史の入試問題って「教科書」から出題されるんです - イクスタ | |

| 詳説 日本史研究 | |
| 教科書の3倍の細かさ 東大一橋の記述対策 | |
| おすすめ度 | 9.0/10 |
| レベル | 共通テスト:50〜90点 |
| 価格 | ¥2,750 |
| 購入 | Amazon |
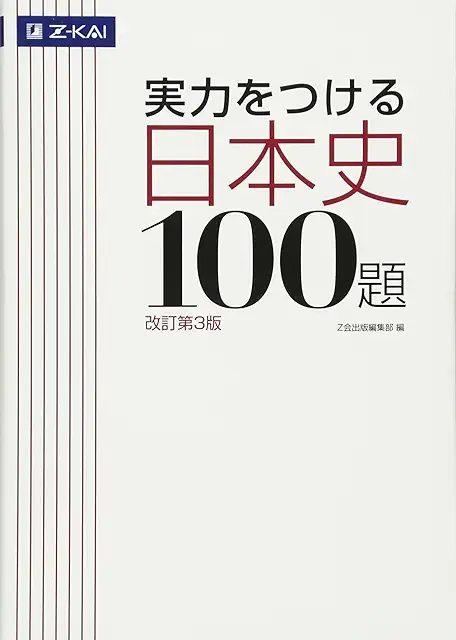
| 実力をつける 日本史100題 | |
| 全時代の入試問題形式 | |
| おすすめ度 | 8.5/10 |
| レベル | 共通テスト:50〜90点 |
| 価格 | ¥1,430 |
| 購入 | Amazon |
| 僕が独学から早稲田合格まで伸ばしたメイン、Z会日本史100題のおすすめの使い方 - イクスタ | |

| はじめる日本史 要点&演習 | |
| 最重要項目の知識と理解チェック | |
| おすすめ度 | 6.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜50点 |
| 価格 | ¥1,100 |
| 購入 | Amazon |

| HISTORIA[ヒストリア] 日本史精選問題集 | |
| 全時代の入試問題形式 | |
| おすすめ度 | 8.0/10 |
| レベル | 共通テスト:50〜90点 |
| 価格 | ¥1,650 |
| 購入 | Amazon |

| 基礎問題精講 | |
| 基礎〜標準レベルの知識と文章題 | |
| おすすめ度 | 6.0/10 |
| レベル | 共通テスト:30〜70点 |
| 価格 | ¥1,210 |
| 購入 | Amazon |
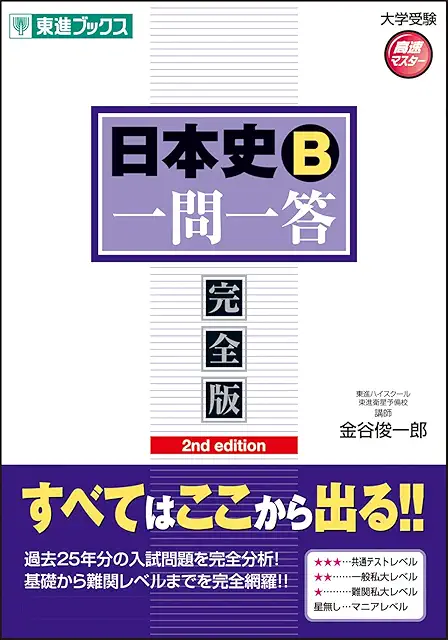
| 日本史B 一問一答 完全版 | |
| 一問一答形式で全単語網羅 | |
| おすすめ度 | 6.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜90点 |
| 価格 | ¥1,078 |
| 購入 | Amazon |
| 【日本史】一問一答だけで共通テスト9割と早慶の合格点が取れてしまった邪道な勉強法 - イクスタ | |

| 日本史 用語集 | |
| すべての用語を文章で解説 | |
| おすすめ度 | 10.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜100点 |
| 価格 | ¥1,012 |
| 購入 | Amazon |

| 流れと枠組みを整理して理解する | |
| 最重要項目を深く理解する | |
| おすすめ度 | 10.0/10 |
| レベル | 共通テスト:〜60点 |
| 価格 | ¥1,430 |
| 購入 | Amazon |
| 「流れと枠組みを整理」日本史、こんな参考書が欲しかった!共テ〜最難関までおすすめ - イクスタ | |

| 時代と流れで覚える日本史用語 | |
| 最重要単語をまとめてチェックする | |
| おすすめ度 | 7.5/10 |
| レベル | 共通テスト:〜60点 |
| 価格 | ¥1,320 |
| 購入 | Amazon |

| 詳説 日本史図録 | |
| 複雑な仕組みや構図を整理し直す | |
| おすすめ度 | 9.5/10 |
| レベル | 共通テスト:50〜80点 |
| 価格 | ¥990 |
| 購入 | Amazon |
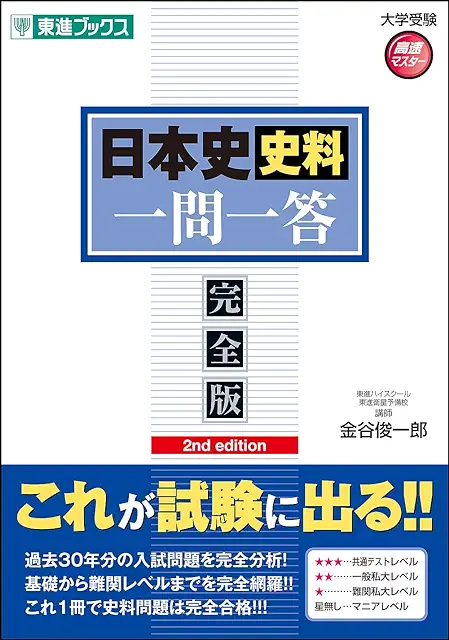
| 日本史史料 一問一答 完全版 | |
| 難関私大に頻出の史料を対策する | |
| おすすめ度 | 6.0/10 |
| レベル | 共通テスト:40〜80点 |
| 価格 | ¥1,078/td> |
| 購入 | Amazon |
イクスタとは
イクスタとはYouflex株式会社の土井万智(どいまさと)がほぼ1人で運営する、はじめての大学受験を成功させるためのプラットフォームです。普通に予備校にいって普通に勉強するだけでは難関大学に合格できないという現実を、どう打破するか。第一志望に合格する15%に入るためには、どう違いを作るか。毎年、1年間一人一人の受験生に毎週の面談で密着すると、実際の事実と世間で理解されている情報の乖離がある。このビジョンをもとに、Webの記事、Youtube動画、書籍、オンラインコーチングという4つの柱で独学の受験生を支援します。
イクスタの創業者、土井による論理的・戦略的な受験計画と戦略の作成
過去問に入る時期や基礎完成の時期などいつ何をやればいいか、完全にコントロールできるようになる必要があります。

> 論理的で抜け漏れのない受験計画の立て方が分かる イクスタコーチ
日本史











 英語の勉強法
英語の勉強法 数学の勉強法
数学の勉強法 現代文の勉強法
現代文の勉強法 古文の勉強法
古文の勉強法 化学の勉強法
化学の勉強法 物理の勉強法
物理の勉強法 世界史の勉強法
世界史の勉強法 英語の参考書
英語の参考書 数学の参考書
数学の参考書 現代文の参考書
現代文の参考書 古文の参考書
古文の参考書 化学の参考書
化学の参考書 物理の参考書
物理の参考書 日本史の参考書
日本史の参考書 世界史の参考書
世界史の参考書 土井の受験攻略本
土井の受験攻略本 Youtubeチャンネル
Youtubeチャンネル 受験カレンダー
受験カレンダー コーチング
コーチング